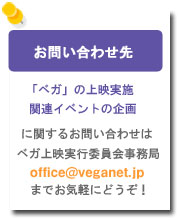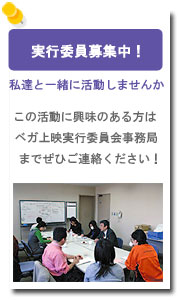ベガで“つながる”ひと・まち・時代 − 戦場に輝くベガ上映実行委員会ウェブサイト

国際フォーラム「巡回展のはこぶもの−その歴史と未来」 登壇とポスター発表&ミニ展示

国際フォーラムの内容
2008年12月23日、九州大学ユーザーサイエンス機構ミュージアム研究会主催の国際フォーラム(於:福岡市博物館講堂)に、「戦場に輝くベガ」と委員会の活動が“巡回展”の視点で取り上げられ、制作者である山梨県立科学館の高橋真理子さん、当時の共同制作者の跡部浩一さん(甲府市立山城小学校教諭)が登壇し、委員会もポスターとミニ展示で参加しました。60名程度の参加者でした。
登壇と、ポスター発表&ミニ展示で、参加された方にベガの内容と委員会の活動を少しでも広めることができた様に思います。
「失われつつある」という観点で言えば、私たちのベガの向き合う「戦争の記憶」と、九州大学ミュージアム研究会が取り組む「クジラと人の関わり(捕鯨を含む)」は、重なり合うことが多く、互いに刺激しあうことのできる場となりました。また、他の登壇者による巡回展の事例報告からも、巡回展に関わる共通の課題や可能性を見出すことができるものとなりました。
国際フォーラムとして、ジョージワシントン大学のキャロル・スタップ博士(博物館教育学)を招き、博物館教育の見方から「巡回展がはこぶものは何か?」に迫るものともなりました。
メッセージやそれに伴う大切な展示コンテンツを「保持」(Keep)することと、巡回する地域のあり方やそれまでの取り組みの欠点から、恐れずに「改革」(Change)すること、この2面のバランスの大切さは、ベガの巡回を通して重要なことと同じように実感できることです。
九州大学の「クジラとぼくらの物語」展は、システマティックに巡回を発想し、また実行もしていて、学ぶことが多いものでした。何かの機会に一緒にできることを探して行きましょう!と話しています。


国際フォーラム開催要項
■日時
2008年12月13日(火)10時〜17時
■場所
福岡市博物館 講堂
■主催
九州大学ユーザーサイエンス機構 ユーザーサイエンス部 ミュージアム研究会
■協力
環境学習施設ネットワーク(E L C Net)/福岡市博物館
■プログラム
第一部:博物館教育の成長と巡回展
10:00〜10:10
開会挨拶 高田浩二氏(マリンワールド海の中道)及びプログラム説明(九州大学ミュージアム研)
10:10〜10:20
福岡市博物館の展示コンセプト 会場側挨拶(鳥巣京一氏)
10:20〜10:50
基調講演1 キャロル・スタップ博士「米国の博物館教育〜その理論と実践の歴史〜」
10:50〜11:00
質疑応答
11:00〜11:40
事例1:巡回展「クジラとぼくらの物語」(清水麻記/加留部貴行)
11:40〜12:10
クジラ展第1回〜6回 模型紹介ツアー(黒澤茂樹)
第1回目 座間味
第2回目 福岡 有田寛之 氏(国立科学博物館 学習課)
第3回目 大阪 村瀬美穂 氏(OCA大阪コミュニケーションアート専門学校)
第4回目 和歌山 櫻井敬人 氏/中江環 氏(太地町立くじらの博物館)
第5回目 福岡 入川暁之 氏(サンゴ研究家 サンゴくん)
12:10〜12:40 福岡市博物館常設展見学
第二部:巡回展示が運ぶもの〜その歴史とケーススタディ〜(仮題)
13:30〜13:50
事例2:国立科学博物館巡回展 南極展(都川 匡史 氏)
13:50〜14:05
心にのこる巡回展ベスト10 発表
14:05〜14:30
事例3:林原自然科学館巡回展 恐竜展(井島真知 氏)
14:45〜15:10
事例4:「 昆虫記」刊行100年記念日仏共同企画「ファーブルにまなぶ」(布谷和夫 氏)
15:10〜15:35
事例5:山梨県立科学館 戦場に輝くベガ( 高橋真理子 氏・跡部浩一 氏)
15:45〜17:00
総括 これからの博物館と巡回展
17:45〜19:15
懇親会 会場:世界のお茶ルピシア福岡店

このサイト内にあるテキストや画像の無段転載・使用はご遠慮ください
Copyright(C)2006-2009 Vega Committee All Rights Reserved.